子供の親権の決め方とは?判断基準と決まるまでの流れ
親権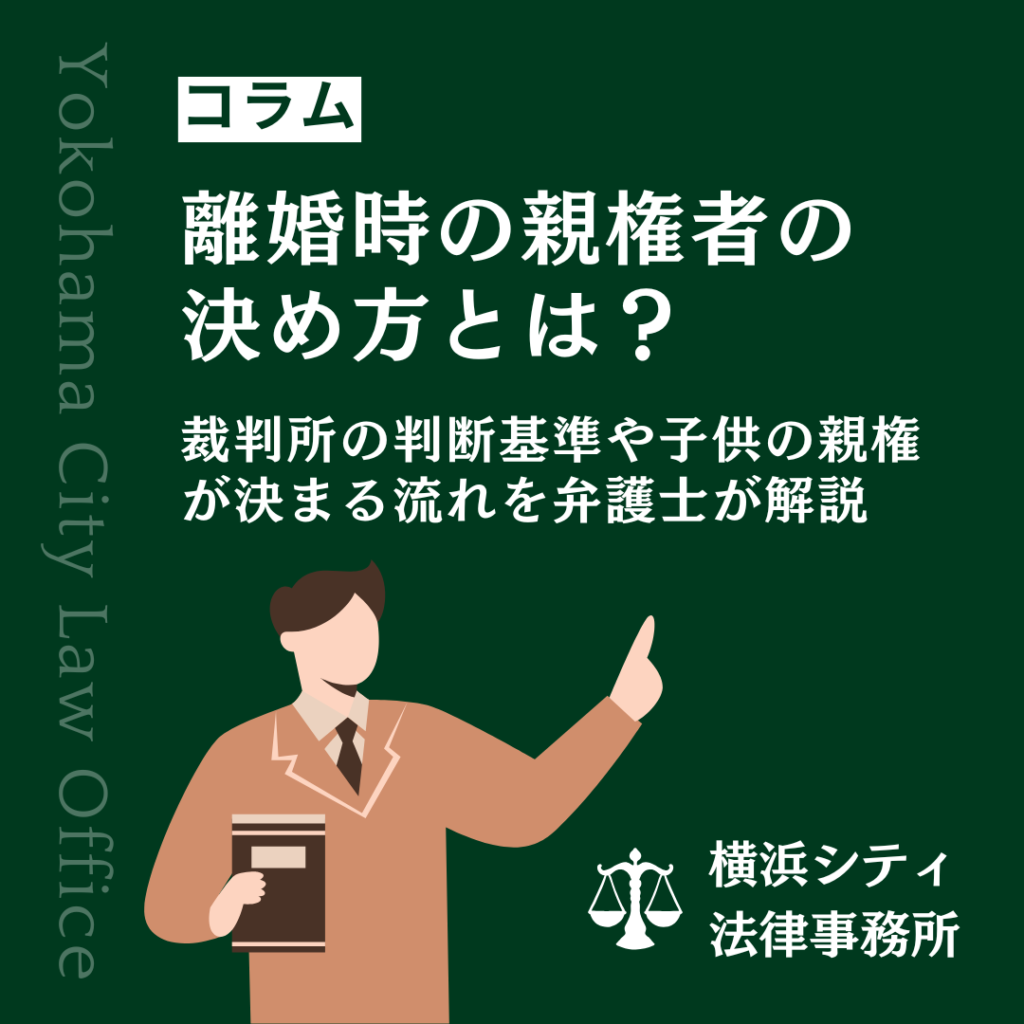
未成年の子供がいる場合、婚姻時は共同親権ですが、離婚をする際には必ず夫婦のどちらか一方を子の親権者をして定めなければなりません。
本記事では、親権者の決め方や、有利に親権を獲得する方法について、裁判所の判断基準から、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説します。
目次
子どもの親権とは?
まずは、そもそも親権とは何なのかについて、ご説明します。
親権とは、未成年の子の財産管理、身上監護に関する権利と義務のことです(権利だけでなく、義務でもあります)。
子の成人年齢は18歳ですので、子が18歳に達するまでは、親権者は子の財産管理、身上監護をする権利義務があるということです。
財産管理権
財産管理権とは、その名のとおり、子供の財産を管理する権利義務のことです。
単に子供の預貯金等の財産を管理するだけでなく、売買契約等の子供の財産に関する法律行為を代わりに行うことができます。
また、子供が親の同意なく行った財産に関する法律行為について、取り消しをすることができます。例えば子供が親に黙って買い物をしたりゲーム課金を行った場合など、この取消権を行使して返金を求めることができる場合があります。
身上監護権
身上監護権とは、未成年者の生活を監護し、教育する権利義務です。簡単に言えば、子供と一緒に生活することです。単に監護権と呼ぶこともあります。
身上監護権には、子供の住む場所を決める権利(居所指定権)や職業を許可する権利(職業許可権)、氏の変更や相続の承認・放棄等を代理する権利(身分行為の代理権)が含まれています。
以前は子を懲戒する権利(懲戒権)が身上監護権に含まれていましたが、児童福祉の精神に反し、児童虐待の口実になるとの批判を受け、令和4年12月16日施行の改正民法により、懲戒権についての規定は削除されました。
以上が親権の内容です。
婚姻時には、両親は共同して親権を行使するものとされております。
他方、日本では離婚後は単独親権であり、離婚時には必ず親権者を父母どちらか一方に定めなければならないと法律に規定されております。
つまり、どちらが親権を取得するかについて争いになっている場合、親権者を決定せずに、先に離婚することはできません。離婚届にも子の親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚届けは受理されません。
なお、離婚する際には、財産分与や慰謝料などが争いになることがありますが、これらについては離婚時に決まっていなくてもよく、先に離婚をしてから決めることも可能です。
親権と監護権を分けられるか
親権は譲るが監護権は譲れない、あるいは監護権は譲るが親権は譲れないと主張して、親権や監護権を夫婦どちらが取得するかで争いになることがあります。
そもそも親権者と監護権者を別々に決めることはできるのでしょうか。
結論としては、親権者と監護権者は、別々に定めることは可能です。
例えば、親権者である父母の一方が遠方にいて適切に子供の監護をすることができない場合、もう一方を監護権者と定め、子供の監護を行うことがあります。
このように、親権から監護権を切り離し、親権者は子供の財産管理や重要な法的決定を行い、監護権者は子供の日常的な監護養育を行うことがあります。
もっとも、裁判所が親権者と監護権者を別々に定めることは多くありません。
なぜなら、子供を監護していない場合に比べ、実際に子供を監護している方が子供の状況を正確に把握できるため、適切に親権を行使することができます。
また、親権者と監護権者が別々になる場合には、責任の所在もあいまいになり、子供が混乱したり精神的に不安定になる可能性もあります。
そのため、基本的には親権者と監護権者は別々に定めません。別々に定めた方が子供の利益になると裁判所が判断した場合には、例外的に親権者と監護権者を別々に定めることがあるのです。
親権はどのような流れで決まるか
協議
離婚をするにあたり、まずは夫婦間で協議をし、親権者を定めます。
これまでどちらか一方が子供の監護をしてきた場合には、大きな争いもなく親権者が決まることは多いです。
もっとも、そのような夫婦ばかりではありませんし、社会的に共働きの夫婦が増えてきたこともあり、子供の監護を夫婦両方で分担しているケースが最近は多くなっております。そういった場合には親権について争いになることも多く、協議が成立しないことも多々あります。
調停
協議が成立しない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることとなります。
調停は、調停委員2名と裁判官1名から構成される調停委員会を通して、夫婦双方が話し合いでの解決を目指す場です。
また、家庭裁判所の職員である調査官(家裁調査官)が、子供の監護養育に関する事実調査を行う場合があります。
具体的には、これまでの監護状況や現在の監護状況を夫婦や関係者から聞き取ったり、裁判所の児童室で子供と接しながら子供の考え方を直接聞き取ったり、学校を訪問して担任の先生から子供の特性や親子関係を聞き取ったり、家庭訪問をして監護状況の確認をしたりする等の方法で調査を行います。
そのような調査を経て、調査官から監護に関する調査報告書が裁判所に提出されます。こういった調査官の報告書を参考にしながら、裁判所は夫婦間の意見を調整し、合意形成を目指します。
夫婦間の合意が整えば、調停成立ということになります。合意した内容(親権者やその他離婚条件)を調停調書に記載し、親権者を定めて離婚が成立します。
調停が不成立となった場合には、通常は訴訟に進みますが、稀に次の審判手続に進む場合があります。
審判
審判では、協議や調停と異なり、夫婦間で意見がまとまらない場合でも、裁判所が夫婦のどちらか一方を親権者と定めます。
しかし、審判に対しては2週間以内に当事者が異議申し立てをすることができ、異議申し立てがされた場合、審判は効力を失います。
親権が決まらず調停が成立しないケースでは、双方が親権を強く希望していることが通常です。審判がされても結局異議申し立てがされることが多いと考えられることが、審判が利用されるケースがほとんどない理由とも言われます。
審判が利用されるのは、離婚については夫婦双方が合意しているが、親権については決まっていない状況で、親権者の決定を審判に委ね、その決定に従う意向を夫婦双方が示している場合があるとされておりますが、実務上はほとんど見られません。
このように、調停が不成立となった場合には、審判に移行するのではなく、夫婦の一方から訴訟を提起されることが通常です。
訴訟
協議、調停を経ても夫婦間で親権について合意に至らない場合には、最終段階として離婚訴訟が提起されることとなります。
訴訟では、裁判官の判断により、判決で夫婦どちらか一方が親権者と指定されることとなります。
判決に不服がある場合には控訴することができ、控訴審での判決にも不服がある場合には上告ができます。
もっとも、上告が認められるのは憲法違反や最高裁判所の判例に反している場合、重大な手続違反等の場合に限られているため、実際には控訴審までで紛争が終結することが多いです。
裁判所による親権の判断基準
裁判所が親権者を定めるにあたり、重視するポイントをご説明します。
新権に争いがある場合には、これらのポイントを意識して主張していくことで、自身が親権者にふさわしいことを裁判所に示すことができます。
子の利益
親権者を定めるにあたり、裁判所が最も重視するのは、子の福祉、すなわち夫婦どちらが親権者になった方が子の利益になるか、ということです。
以下に挙げる項目も、裁判所が「夫婦のどちらを親権者にすれば子の利益になるか」ということを判断する要素の一部といえます。
親権に争いがある場合、親権を取得するために自分本位な行動をしてしまう方もいらっしゃいます。しかし、裁判所は子の利益を最優先に考えるため、親権を取得するためにも、子の利益になるのはどのようなことなのか考えることが必要です。
これまでと現在の監護状況
これまで夫婦のどちらが子供の監護をしてきたかというのは、離婚後も子供を適切に監護していくことができるのか否かを判断するのに大きな要素となります。
食事やお風呂の世話、寝かしつけや学校の準備、保育園や幼稚園の送り迎え、連絡帳の記入、塾の送迎、保護者としての学校との連絡役、病院の付き添い等、監護の内容は多岐にわたるため、夫婦がそれぞれどのような監護をしてきたかを整理し、これまでの監護実績を判断します。
親権に争いが生じている状況では、既に夫婦が別居している場合も多いです。離婚後は夫婦共同ではなくどちらか一方が子供の監護をすることが多いため、別居をして配偶者がいなくても子供の監護ができているという状態は、離婚後も継続して適切に子供の監護をすることができることを示しているといえます。
また、裁判所は子供の監護状況が変化した際に子供に悪影響が生じることを懸念します。そのため、適切に子供の監護ができている現在の状況を敢えて変化させてまで、子供の監護者をもう一方の非監護親(非同居親)に変えることは避ける判断をすることが多いです。
現在適切に監護ができているという実績は、親権者を定めるにあたっての非常に重要な要素であるといえます。
監護環境
将来的に安定した生活環境を確保できるかという視点で、経済力も考慮されます。仮に収入がなく、賃貸物件を追い出される危機にあるという状況でしたら、監護環境として適切とは言えないでしょう。
もっとも、子の監護に必要な費用については養育費である程度カバーできる部分ですので、裁判所の判断としてそこまで重視されるポイントではありません。
監護者がしっかりと子の監護をしていくことができるか、また、夫婦どちらの監護環境が将来的に子にとって利益があるのかという点を、裁判所は重視します。
一例として以下のような場合には、裁判所も将来的な監護環境が不適切だと判断する場合があります。
現在は一時的に仕事を離れて子供の監護ができているが、近いうちに夜勤の多い職場に勤務を開始する場合、乳幼児の監護環境としては適切とまでは言い難いでしょう。
また、近いうちに遠方に引っ越す予定があるが、子供が通っている学校を事情により変えられない場合、引っ越し先から子供の通う学校がとても遠く、往復で何時間もかかるような場合には、子供の負担が大きく、監護環境として適切とはいい難いでしょう。
上記のように監護環境が必ずしも適切とはいえない場合には、子供のために適切な監護環境を用意し、相手より自分の用意する監護環境の方が子供の利益になることを示す必要があります。
例えば監護者が夜勤で夜間は家を空けるとしても、同居している監護補助者(祖父、祖母、叔父、叔母等)がいる場合には、監護者に変わり、子供の面倒をみることができます。
登校にあたって子供の負担が大きい場合には、引っ越し先を学校の近くに変更して子供の負担を減らし、より子供の利益になるように監護環境を整えることが考えられます。
なお、監護補助者はあくまでも補助者です。
なにより大切なのは、親である監護者自身が子の監護を適切にすることです。祖父母が元気で常にこどもを見てくれるからといって、監護者が子の監護をほとんどできない場合には、裁判所としても監護環境が不適切だと判断することになるでしょう。
面会交流に対する寛容性(フレンドリーペアレントルール)
子の利益として大切なのが、子が両親からの愛情を直接感じられることです。父親母親それぞれからの愛情を受けることで、子は精神的にも健全に成長することができると考えられています。
そのため、夫婦の一方が親権を獲得した場合に、もう一方の親と子が適切に面会交流を行うことができるか否かという点も、裁判所は重視します。
夫婦間で紛争が生じている場合には、子供を配偶者に会わせたくないと考える方もいるでしょう。
しかし、そのような方が親権者になった場合、子がもう一方の親と適切に面会交流ができないことを懸念し、子の健全な成長を妨げると考え、親権者として不適格だと裁判所が判断する可能性があります。
夫婦間の紛争と子が面会交流により受ける利益は別のことであることを理解し、面会交流は適切に実施するべきです。
子の意思
家事事件手続法には、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を尊重しながら審判及び調停をすることが求められています(家事事件手続法第65条、第258条1項)。
また、家事審判で15歳以上の子の親権を定める場合には、子の陳述を聞かなければなりません(家事事件手続法第169条2項)。
親権者が父母のどちらになるかというのは、子にとって非常に大きな影響があります。そのため上記のとおり、子の意思を尊重し、15歳以上の子については陳述を聞かなければならないことも定められているのです。
もっとも、幼い子の場合には、自身にとってどちらが親権者となるのが適切か判断することは困難です。幼い子であればその時の監護親の影響も受けやすく、監護親に言われたことをそのまま受け入れ発言するという可能性も高いです。そのため、子の意思全てに従うのではなく、子の意思を尊重しながら、裁判所は子の利益になるように親権者を定めることになります。
15歳以上の子であれば、両親の離婚という事実を概ね理解し、自らの意思でより自身に利益のある親権者を選択することができると考えられます。
そのため、15歳以上の子の親権者を定める場合には、子の陳述を聞き、子の意思によって親権者を定めることが多いです。
兄弟不分離の原則
複数の子供がいる場合、つまり兄弟姉妹がいる場合には、父母のどちらかに全員統一することが、子供のためになるという考え方です。
兄弟姉妹をバラバラにして引き離してしまうと、子供の心理的負担が大きいことから、このような考え方が採られております。
小括
以上、裁判所が親権者を定める際に重視する代表的なポイントをご説明しました。
裁判所が親権者を定める際に考慮する事項は上記の項目に限られるわけではなく、様々な事情を考慮して判断します。
親権の獲得を目指す場合には、上記の項目に縛られることなく、常に子の利益を優先して行動することが大切です。
父親でも親権を獲得できる?
なぜ父親が親権を取得することは困難なのか
世間では、親権は母親が有利で、父親は不利とよく言われます。実際、最高裁判所が発表している令和5年司法統計年報によると、全国の家庭裁判所における「離婚の調停成立又は調停に代わる審判事件」のうち、「子の親権者の定め」をした事件、合計1万6103件のうち、母親が親権者となったのが1万5128件、父親が親権者となったのが1290件であり、父親が親権を取得したのは全体の1割にも満たないことが分かります(なお、子どもが複数いて別々の親権者を定める場合もあるため、事件数と親権者数とがずれています。)。
統計からみても、父親が親権を取得することは難しいのが現実です。
共働きの夫婦が増えたといっても、子供の監護は母親が中心となって行っている家庭の方が割合としては多いです。父親の仕事が忙しく、子供の監護養育を十分にこなすことができない場合には、監護者として不適格であると裁判所に判断されてしまいます。
また、父親の監護の割合が低く、監護は母親が中心となって行っている場合、子供は母親と過ごす時間が長いということです。そうすると、子供も母親の方により懐いていることが多く、子供自身も親権者は母親の方が良いと考えることが多いのです。
さらに、父と母、どちらが親権を取得するのが適切かという問題について、母性優先の原則(母親優先の原則)という考え方があります。
これは、母親と一緒にいることが子の利益になるという考え方です。
現代では、男女平等の考え等から、建前上は母親であるというだけで優先しないことにはなっており、母性優先の原則も、どちらが旧来の母親的役割を果たしているかという視点で見るべきであるという解釈がなされるようになってきておりますが、固定観念が強い裁判官もまだまだ多くいるという印象です。
特に、子供が乳幼児である場合等、幼ければ幼いほど、母親と一緒にいることが子の利益になるという考え方は今なお根強いです。そもそも、母乳育児をしている場合には自然と母親の監護の度合いが強くなるということもあり、乳幼児の親権者の多くは母親とされております。
以上のような理由から、親権について争いがある場合、最終的には母親が親権を取得する結果となることが多いです。
父親が親権を取得するために大切なこと
母親が親権を取得することが多いといっても、上記の統計のとおり、父親が親権を取得することが全くできないわけではありません。
横浜シティ法律事務所が担当させていただいた離婚事件でも、父親が親権を獲得することができたケースはいくつもあります。
(1)監護実績を積むこと
先ほどご説明したように、母親と一緒にいることが子の利益になるという母性優先の原則という考えがあります。それは、父親が働き、母親が中心となって子の監護を行うという生活スタイルが昔は一般的だったためです。それまで母親が中心となって子の監護を行ってきたのだから、離婚後も母親が親権者となり子の監護をするのが適切であるとのことで、母性優先の原則が考えられてきました。
しかし、男女平等の観点から批判があり、また近年は夫婦共働きも増え、子の監護も夫婦で担うことが増えています。そのため、前述したとおり、現代では、形式的に母親を親権者として優先すべきという考えではなく、従来の典型的な家庭で母親が担ってきた「母性」を実質的に有する側が親権者として優先されるという考え方に変化してきました。
例えば妻が働き、夫が専業主夫として中心的に子の監護をしてきた場合には、夫が妻より母性を有するとして、親権者として優先されることとなります。
詰まる所、男女に関わらず、監護実績の多寡が重要ということです。これまでの監護実績が乏しい場合には、しっかりと監護実績を積んでいくことが必要です。
(2)母親に監護者としての問題がある場合
母親に監護者としての問題がある場合にも、父親に親権が認められやすくなります。
具体的なケースを紹介すると、母親に精神上の問題や健康上の問題があり、入退院を繰り返しているような場合や、これまで虐待や育児放棄(ネグレクト)があったような場合です。
このような場合には、母親では子供を適切に監護できないと裁判所が判断する可能性があります。
争いになることが多いのは、母親が不貞行為に及び、浮気をするような親が親権者になるのは納得できないと父親が考えた場合です。
しかし、不倫をしたからといって適切に子の監護をできないという結論には直ちに結びつかないため、親権者を定める上では裁判所の判断に大きく影響しません。
とはいえ、不倫に夢中になるあまり、母親が子供の世話をせず、家に置いて放置してラブホテルや不倫相手の男の家に入り浸っているような場合には、裁判所も母親が親権者として適切でないと判断する可能性があります。
そのような場合には、父親が自宅でしっかりと子供を監護し、監護実績を積み重ねることで、自身が親権者にふさわしいことを裁判所に示すことが大切です。
上記のとおり、父親が親権を得ることはそう簡単ではありません。
しかし、親権を獲得できる可能性が全くないというわけではないため、親権を獲得するために、しっかりと監護実績を重ね、問題がある事項にはひとつひとつ対応し、自身が監護親として適切であることを裁判所に示すことが大切です。
親権者は離婚後に変更できる?
一度親権者を決めて離婚をした後、親権者を変更すること自体は認められております。
もっとも、離婚時に決めた親権者を、両親の合意だけで変更することはできません。
親権者の変更をする場合には、両親が合意していたとしても、家庭裁判所で調停または審判の手続きをする必要があります。
また、一方の親が親権者の変更を求め、両親間で合意が整わない場合も、家庭裁判所の調停または審判の手続を行うことになります。
ただし、親権者の変更は難しいことが一般的です。現在の養育環境で特に問題が生じていないのであれば、わざわざ親権を変更することは、通常子供の利益にならないと考えられるからです。
後で親権者の変更ができるからと安易に考えて、離婚時に親権を譲ってしまうと、後々親権者の変更が認められずに後悔することになりかねません。
現在の親権者が子供を虐待しているなど、親権者としての適格性に欠ける場合や、子供が親権者の変更を望んでいる場合(特に、子供が15歳以上の場合にはその意思が重視されます。)等には、裁判所に親権者の変更を認めてもらえる可能性があります。
裁判所は、ここでも親権者を変更することが「子供の利益」になるかという観点から、親権者を変更すべきかどうか、判断をすることになります。
親権をとれなくても子供に会える
親権者になれなかったとしても、子供と面会交流をすることができます。
面会交流の場所や日時、頻度といった具体的な内容については、子の監護親(同居親)と非監護親(非同居親)が協議で定めることとなります。
そして、協議が定まらない場合には、面会交流調停を申し立て、調停で話し合うこととなります。
裁判所は、非監護親が子供や配偶者に暴力を振るっていたり、子供を連れ去る危険性があったり、子供が非監護親に会いたくないという強い意志を有しているといった事情等がない場合には、月1回程度の面会交流を認めることが多いです。
子供に会いたいあまり、監護親との話し合いができる前に学校や習い事の帰りの子供を待ち伏せしたり、無理やり子供を連れ去ろうとする方がいます。
しかし、そのようなことをすると大きなトラブルになることはもちろん、親権を争う場合にはそもそも監護者としての適格性を疑われることに加え、今後も子供を連れ去る危険性があると裁判所が判断し、将来的な面会交流が認められない可能性も高まってしまいます。
すぐにでも子供に会いたい気持ちはよく分かりますが、監護親との協議をせずに突然子供に会いに行ったり、独断で別居先の自宅に連れ帰ったりするべきではありません。
法律上の適切な手段に則って、面会交流を実現しましょう。
※面会交流については、こちらのページをご参照ください。
「親権の決め方」のまとめ
以上のように、親権者は夫婦間の協議で決めることができますが、協議が整わない場合には裁判所が親権者を決めます。
裁判所が親権者を決める際に重視するポイントは様々ありますが、根底にあるのは、どちらを親権者にするのが子供の利益になるか、という考え方です。
自分が離婚をした際に親権を取ることができるのか、親権を取るためにはどのようなことをすれば良いのか、ご不安な方は多いと思います。
そのような方は、お一人で悩まず、一度弁護士にご相談いただき、親権を獲得するためにご自身にできることは何なのかアドバイスをもらうのが良いでしょう。
横浜シティ法律事務所の弁護士は離婚事件の豊富な経験があり、親権の争いも多数解決してきました。
初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。
※親権・監護権については、こちらのページでも概要を解説しております。


弁護士の山本新一郎と申します。
私は江戸時代より代々医師を生業としてきた家系に生まれ、幼い頃から病気に悩む方々に対して優しい言葉をかけ、懸命に治療をする父や祖父の姿を見て育ちました。
私が弁護士を志した原点もここにあり、法的トラブルに巻き込まれてしまった方々の負担を少しでも軽くしたいと常に考えております。
病気と同じく、法的トラブルも早めにご相談いただければダメージなく解決できるものです。
まずはお気軽にご相談ください。
離婚ひとつをとってみても悩みや答えは十人十色です。
思うまま、感じているままにお話しください。
一緒に悩み、考え、あなたにとって一番の答えを探しましょう。