事実婚とは?財産分与、慰謝料、年金分割、相続はどうなる?
事実婚年金分割慰謝料財産分与養育費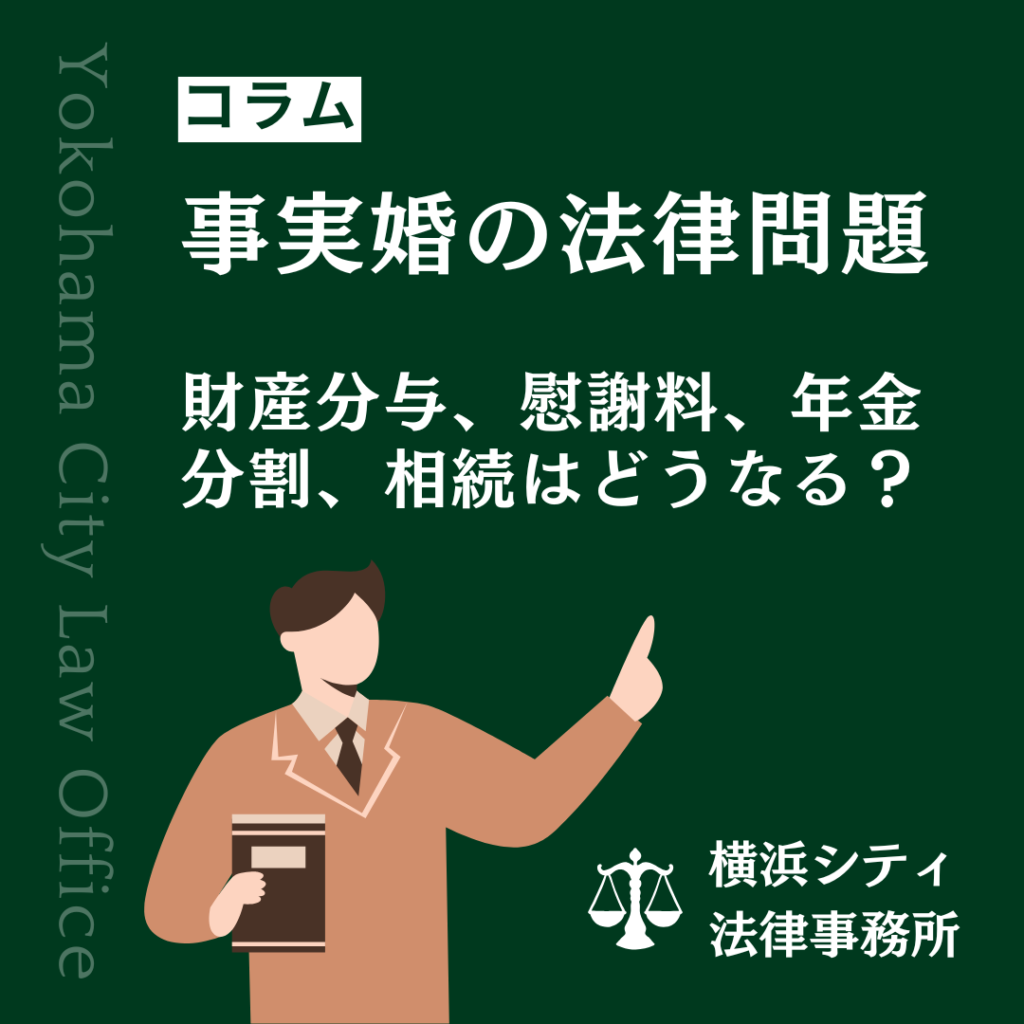
今回は、事実婚に関連する法律上の諸問題、メリット・デメリットについて、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。
近年は夫婦関係の在り方に多様化が進み、法律婚ではなく、事実婚という選択肢を考える方も増えてきています。
内閣府で令和3年度(2021年度)に実施した各種意識調査の結果から、事実婚を選択している世帯は、成人人口の2〜3%を占めているとされております(男女共同参画白書 令和4年版 )。
事実婚においても、法律婚と同じように、健康保険、自治体の行政サービスなどの保障が一定程度受けられます。
しかし、社会上、事実婚は法律婚と異なる取り扱いをされる場面が数多くあります。
本コラムでは、事実婚が法律上認められる条件や、法律婚ではなく事実婚を選択した場合のメリットやデメリット、事実婚を選択された場合にしておくべきこと、事実婚を解消する場合の注意点、事実婚での不倫等、詳しくご説明していきます。
なお、事実婚ではなく内縁という言葉を聞かれたことのある方も多いかと思います。
両者を明確に区別する方もいらっしゃいますが、今回は内縁=事実婚としてお話しいたします。
目次
事実婚と認められるのはどのような場合か
事実婚とは、夫婦生活を営んでいる社会的実体はあるものの、婚姻届を提出していない男女の関係をいいます。
法律婚との違いは離婚届を提出しているか否かですが、法律婚と同様に夫婦生活の実態がなければ、事実婚とは認められません。
法律婚の場合には、婚姻届を提出し、婚姻したことが戸籍に記載されることで、明確に婚姻関係を認めることができます。
しかし、事実婚の場合には、婚姻届を提出せず、婚姻したことが戸籍に記載されないため、「これをしていれば必ず事実婚だと認められる」というものがございません。
事実婚の成立要件
法律上、事実婚の成立要件が明確に定義されているわけではありませんが、一般的には以下の2つが事実婚の成立要件とされています(東京地裁昭和49年7月16日判決など)。
① 婚姻の意思があること
※ここでいう婚姻意思とは、婚姻届を出す意思ではなく、社会一般で考えられているような夫婦生活を継続して送る意思です。
② 客観的に見て、夫婦生活と認められるような共同生活を送っていること
どのような場合に①②が認められるかですが、その男女間の経歴、生活状態、同居期間、第三者の認識などを含め、様々な事情を総合考慮して判断されることになります。
具体的には、以下のような事情があると、事実婚と認められやすくなります(ただし、何個の事情に当てはまれば必ず事実婚と認められるというものではなく、ケースごとの総合判断になります)。
・新婚旅行に行った
・結納をした
・結婚式を挙げた
・婚約を交わした
・同居期間が長期にわたっている
・家計が同一である
・継続的な肉体関係がある
・こどもが誕生した、その子を認知した、一緒に育てている
・住民票が同一世帯となっている
・住民票に「未婚の妻」、「未婚の夫」と記載されている
・親族や周囲の人物等から、夫婦として扱われている(たとえば、冠婚葬祭に夫婦として出席している等)
・パートナーが行う契約や申込の書面に、関係を妻(夫)と記載している
・社会保険の第3号被保険者となっている
・当事者間で事実婚をする旨の書面を交わしている
一方で、上記のような各種婚姻儀礼が行われていない、同居をしていない(もしくは同居していても同居期間が短い)、家計が別になっているというケースでは、事実婚が認められにくくなり、単なる男女の交際関係(カップル)と判断される可能性が高くなります。
もっとも、同居していない場合でも、それに理由がある場合(たとえば仕事上の単身赴任、病気療養等)で、生活費の分担や日常的な協力関係を続けていたのであれば、客観的に見て、夫婦生活と認められるような共同生活といえることもあるでしょう。
以下では、具体的な裁判例で事実婚が認められたケースと、認められなかったケースをそれぞれ紹介いたします。
<事実婚が認められたケース(東京地方裁判所判決平成16年8月25日 )>
裁判所は、以下の①〜⑥などの要素を踏まえ、事実婚の成立を認定しました。
※原告が女性、被告が男性です。
①被告は婚姻の申込みを行い、原告はこれを承諾し、
②これに基づく同居生活が3年以上継続していること、
③原被告は同居先のマンションに住民票上の住所を移しているばかりか、
④同居生活の間も宿泊付きの旅行に行ったり、
⑤原告の実家の墓参りをしたり、
⑥原告の前夫との間の娘に面会するなどしている
<事実婚が認められなかったケース(最高裁判所第一小法廷判決平成16年11月18日)>
「パートナーシップ関係」にあった男女間におけるケースにおいて、裁判所は、二人の関係が16年に及ぶ関係であることや2人の子供が生まれたことを指摘しつつも、
①同居をしていなかったこと、
②財産関係が別々であったこと、
③両者が意図的に婚姻関係を回避していた事実があったこと
などを踏まえ、「婚姻及びこれに準ずるものと同様の存続の保障を認める余地がない」として、事実婚の成立を否定しました。
この裁判例を参考にすると、交際期間が長かったり、子供が生まれただけでは足りず、同居や家計の同一性等、その他の事情次第では事実婚が認められない場合があることがわかります。
婚姻障害がある場合でも、事実婚が認められるか
婚姻障害とは、法律に定められている、結婚することが許されない事由のことです。
具体的には、以下のとおりです。
① 婚姻適齢(現在は男女ともに18歳以上となりました) 民法第731条
② 重婚の禁止(一夫一妻制) 民法第732条
③ 近親婚の禁止(近親とは直系血族、直系姻族、3親等内の傍系血族) 民法第734〜736条
※以前民法第733条に定められていた「再婚禁止期間」=女性は離婚後100日間(昔は6ヶ月間でした)再婚できないという規定は、改正により削除されました。
※以前民法第737条に定められていた「未成年者の婚姻に関する父母の同意」は、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、改正により削除されました。
婚姻障害がある場合は、婚姻届けは受理されません(もし誤って受理されてしまったとしても、婚姻が取消されることになります)。
では、このような婚姻障害がある場合にも、事実婚であれば認められるのでしょうか。
①婚姻適齢
古い判例ですが、裁判所は婚姻適齢に達していない場合でも、事実婚の成立を認める判断をしております(大審院大正8年4月23日判決)。
②重婚
古い判例(大審院大正9年5月28日判決)では否定されたものの、最近では、法律婚が破綻状態にある場合には、重婚であっても、内縁(事実婚)に準じた効果を認めようという考え方が大勢になってきています(東京地裁昭和62年3月25日判決等)。
もっとも、社会保障上の給付については、慎重な判断がなされるでしょう。
③近親婚
夫の連れ子と夫婦になった事案について、反倫理的として事実婚を認めなかった判例(最高裁昭和60年2月14日判決)があります。
他方で、当初内縁関係に入った態様に不当な点が見当たらず、42年の長期にわたって安定した夫婦関係を築いた叔父と姪の事案について認められた事案もあります(東京地裁平成16年6月22日)。
近親婚については、動機や経緯、その態様等により、ケースバイケースの判断がなされているといえます。
同性同士で事実婚が認められるか
同性カップルの方から、同性同士で事実婚が認められるか、というご質問を受けることがあります。
しかし、日本では、同性同士の法律婚(同性婚)が認められておりません。事実婚に法的保護が与えられるのは、法律婚に準じる関係がある(準婚)からであり、法律婚で同性婚が認められていない以上、事実婚でも同性婚は認められておりません。
事実婚を選択するメリットについて
夫婦別姓
日本では法律婚をするためには夫婦同姓にする必要がありますが、事実婚の場合には同姓になりません。夫婦別姓にしたい方にとっては、この点は大きなメリットといえます(反対に、夫婦や家族で同姓を用いたい方にとっては、デメリットとなります。)。
なお、法律上は「姓」ではなく「氏」という用語を用います。
親族との距離
法律婚の場合には、配偶者の両親や兄弟などの3親等内の姻族は法律上の親族となります(民法725条3号)。そのため、新年には挨拶のために実家に行くなど、親族間の付き合いをする場合もあるでしょう。
しかし、事実婚の場合には法律上の親族とはならないことから、法律婚に比べてお互いの親族との関係が希薄な場合もあり、人付き合いを面倒に感じがちな方や、周囲に干渉されずに夫婦だけで生活していきたい方にとっては、法律婚に比べてメリットを感じることがあるかもしれません。
離婚時の戸籍の記載
法律婚の場合には、離婚をすると、離婚したことが戸籍に記載されます。
しかし、事実婚の場合には、そもそも婚姻したことが戸籍に記載されません。同様に、離婚したとしても、戸籍に離婚したことは記載されません。
婚姻するときから離婚のことを考える方は多くはないと思いますが、戸籍の記載を気にされる方にとっては、事実婚を選択することに一定のメリットがあるといえます。
事実婚に適用される法律
事実婚であると認められる場合には、法律婚に準じて、以下のような民法の規定が適用されます。
① 同居義務、相互扶助義務(民法752条、760条)
② 貞操義務(民法770条1項1号)
③ 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
④ 夫婦の共有財産(離婚時の財産分与)(民法762条2項)
事実婚を選択するデメリットについて
婚姻関係が認められない可能性について
事実婚と認められれば、法律婚に準じた扱いを受け、上記のとおり民法の適用もあります。
しかし、事実婚であると認められない場合には、そのような規定の適用を受けることができません。
婚姻関係が認められない可能性があること自体が、事実婚のデメリットであるといえます。
相続について
法律婚の場合には、配偶者には相続権が認められております(民法890条)。
しかし、事実婚の場合には、相続権が認められません。
税務上の優遇について
法律婚の場合には、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」といった税制上の控除を受けることができます。
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である場合、その分の「医療費控除」を受けることもできます。
また、法律婚であれば、相続や贈与を受けた場合に、相続税や贈与税の優遇があります。
しかし、事実婚の場合には、このような婚姻に関連する税金の優遇措置を受けることができません。
入院手術をする際の家族の署名などについて
社会生活の中で、家族の署名を求められる場面もあるでしょう。
例えば、病院での入院手術の際に、家族の署名を求められることがあります。法律婚の場合には配偶者が署名をすることができますが、事実婚の場合、配偶者であると医療機関が判断できないときは、署名をすることができない場合があります。
婚姻費用について
法律婚の場合、夫婦が別居した場合も、離婚が成立するまでの間、配偶者に婚姻費用(生活費)の請求をすることができます。
事実婚の場合も、事実婚の期間中は、パートナーに婚姻費用の請求をすることが可能です。もっとも、別居をした場合、その時点で事実婚の関係が解消されたとみなされることが多いため、別居後に婚姻費用を請求することは困難な場合が多いでしょう。ただし、事実婚の解消を前提としない別居、たとえば単身赴任等の一時的な別居の場合には、婚姻費用を請求することができます。
事実婚と子どもについて
父親について
法律婚の場合、婚姻中に妻が妊娠した子は、原則として夫の子であると推定されます(民法772条1項)。
しかし、事実婚の場合にはこの規定が適用されず、非嫡出子(婚外子)となり、夫の子であると推定がされません。
そのため、事実婚の夫と子に法律上の親子関係を生じさせるためには、夫に子の認知をしてもらう必要があります。夫が子の認知をしない場合には、妻が夫に対して認知の訴えを提起する必要があります。
親権について
現在の民法では、法律婚をしている場合にのみ、両親が共同親権を持つことが認められております。
このため、事実婚の場合、子どもの親権者は母親のみとなります(子の出生とともに、母親が親権者となります。)。
なお、家庭裁判所で親権者変更の手続きを取り、認められた場合、父親が親権者となることも可能です。ただし、その場合には、父親の単独親権となり、やはり共同親権となるわけではありません。
子供の姓と戸籍について
事実婚の場合、子どもは、出生と同時に、母の戸籍に入るため、母親と同じ姓になります。
もっとも、家庭裁判所で「子の氏の変更」の手続をすることで、父の戸籍に移して、父の姓を名乗ることもできます。
事実婚を選択した場合にしておくべきことについて
事実婚であることの証明について
事実婚のデメリットには、上記に挙げたような法律の適用の有無や入院手術の際の署名など、夫婦関係を証明できないことに起因するものがあります。
そのため、事実婚であることを外部に明確に示すことで、そのようなデメリットを解消することに繋がります。
単なる同棲ではなく事実婚であることを示すために、親族など周囲の人間に報告をしたり、結婚式を挙げたり、事実婚であることを確認する契約書を作成するなど、様々な方法が考えられますが、公文書である住民票に夫婦関係を記載してもらうことが有用です。
夫婦同一世帯にするために住民票の変更届をする際、市区町村の窓口で事実婚とすることを告げ、世帯主ではない方の続柄に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載してもらいましょう。
住民票という公的な書類に明確に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載することで、夫婦であることを社会的に示す根拠のひとつになります。
相続にかわって遺産を残す方法
事実婚の場合には、夫婦間に相続権がないことをご説明しました。
そこで、夫婦の一方が亡くなった場合に備えて、夫婦間で生前贈与や死因贈与の契約を締結したり、夫婦のもう一方に遺贈する旨の遺言書を作成したりしておくことが考えられます。
もっとも、最低限の相続割合が法律上認められている親族がいる場合には(遺留分権利者といいます。(民法1042条))、必ずしもすべての財産を受け取ることができるわけではありません。また、贈与税や相続税について、配偶者としての優遇措置を受けることができないというデメリットはなお残ることになります。
事実婚を解消する場合の注意点について
解消にあたっての条件を取り決める
取り決める事項
①財産分与
事実婚の場合も、法律婚のように、財産分与を請求できます
財産分与の割合は、法律婚と変わらず、原則2分の1ずつです。
②慰謝料
不貞行為やDV等があり、相手方のせいで事実婚を解消せざるを得なくなった場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。
③養育費
子供がいれば、養育費も請求できます。
認知してもらっていない場合には、法的な養育費支払義務はありませんので、認知を求めることも検討しましょう。
④面会交流
事実婚を解消しても、親子であることは変わりませんので、同居していない親からは、子供との面会交流を求める権利があります。
事実婚の解消時には、子供との面会交流の頻度や方法等についても、話し合っておくとよいでしょう。
協議書や公正証書を作成する
事実婚を解消するにあたっては、上記のような事柄について、しっかりと条件を取り決める必要があります。
そして、条件がまとまった際には、後で言った言わないで揉めないよう、協議書や公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。
当事者間で話し合いがまとまらない場合
事実婚の解消にあたっては、法律婚の離婚と同様、取り決めるべきことが多くあります。
また、法律婚と異なり、事実婚が成立しているか否かが争点になることも多いです。
そのため、必要に応じ、法律の専門家に相談や依頼をすることもご検討いただくとよいでしょう。
また、家庭裁判所に「内縁関係調整(解消)調停」を申し立て、調停委員を通して調整を図っていくことも可能です。
※調停については、下記の裁判所のウェブサイトもご参照ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_19/index.html
事実婚でも年金分割は可能
法律婚の場合、離婚後に、合意分割や3号分割という方法で、婚姻中の厚生年金の払込記録を、夫婦で原則2分の1ずつ分割することができます。
(年金分割の詳細については、こちらのコラムで解説をしていますのでご参照ください。)
事実婚の場合は戸籍に記録がないため、いつからいつまで事実婚だったのか、その期間を明確に判断することができません。
もっとも、3号被保険者(第2号被保険者=厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方)であった期間がある場合には、その期間は記録上明らかです。したがって、事実婚でも、3号被保険者であった期間がある場合には、3号分割制度を利用することが可能です。
注意が必要なのは、年金分割の請求期限が、事実婚解消日の翌日から2年間であることです。事実婚を解消された場合には、解消後速やかに、年金事務所に「標準報酬改定請求書」と事実婚の事実があったことを示す資料(「妻(未届)」、「夫(未届)」と書かれた住民票等)、マイナンバーカード(または年金手帳)を提出し、3号分割制度の手続を行いましょう。
なお、3号分割の手続きを行うにあたっては、相手方の合意は不要です。
年金分割の請求対象は厚生年金の報酬比例部分です。国民年金(基礎年金)や、厚生年金基金、確定拠出年金、個人年金保険は対象となりません。
そのため、年金分割ができるのは、配偶者が会社員や公務員で、厚生年金(共済年金)に加入している場合に限られます。そもそも、配偶者が自営業者等で国民年金(基礎年金)にしか加入していない場合、事実婚・法律婚に関わらず、年金分割制度を利用することはできないということになります。
事実婚で不倫があったら慰謝料を請求できる?
①慰謝料の請求は可能
法律婚の場合、配偶者が不貞行為(不倫)に及べば、配偶者とその不貞相手に対し、慰謝料を請求することができます。
事実婚の場合も、法律婚に準じ、その男女間には、民法上の貞操義務が課されることになります。そのため、パートナーに不貞行為があれば、パートナーとその不貞相手に対し、慰謝料を請求することが可能です。
不貞行為が原因で事実婚が解消されることになった場合には、法律婚の場合の離婚と同じく、慰謝料の増額事由ともなります。
例えば、内縁の妻が不倫をし、内縁関係が解消に至った事案で、裁判所は、内縁の妻と、その不倫相手の男性に対して、200万円を支払うよう判示しました(東京地方裁判所判決昭和62年3月25日)。
これに対し、事実婚ではない単なる交際関係の場合、他の異性と浮気をしたとしても、民法上の不法行為には当たらず、慰謝料の請求は困難です。
②不倫相手に対する慰謝料請求は法律婚よりも認められにくい?
事実婚の場合には、法律婚と比較して、不倫相手はその男女間が事実婚をしていることを把握することが容易ではない場合があります。
そのため、事実婚の場合、不倫相手が事実婚であったことを知らず、知らなかったことに過失もないと判断されることが法律婚よりも多く、慰謝料が認められにくいと言われています。
※事実婚の不倫については、こちらのコラムでも解説しております。
まとめ
以上のように、事実婚は社会的には夫婦であるものの、やはり法律婚とは異なる部分が多く存在します。
法律婚とするか事実婚とするか、選択を悩まれた際に、今回のコラムが参考になりましたら幸いです。
そして、法律婚・事実婚どちらを選択されたとしても、夫婦間では様々な法律上の問題が生じるものです。その際には、ご自身のみで判断されるのではなく、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
横浜シティ法律事務所の弁護士は、離婚・男女問題の精通しており、これまで数多くのご相談を解決してきました。
初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。
※上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。


弁護士の山本新一郎と申します。
私は江戸時代より代々医師を生業としてきた家系に生まれ、幼い頃から病気に悩む方々に対して優しい言葉をかけ、懸命に治療をする父や祖父の姿を見て育ちました。
私が弁護士を志した原点もここにあり、法的トラブルに巻き込まれてしまった方々の負担を少しでも軽くしたいと常に考えております。
病気と同じく、法的トラブルも早めにご相談いただければダメージなく解決できるものです。
まずはお気軽にご相談ください。
離婚ひとつをとってみても悩みや答えは十人十色です。
思うまま、感じているままにお話しください。
一緒に悩み、考え、あなたにとって一番の答えを探しましょう。