有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる場合とは?
離婚請求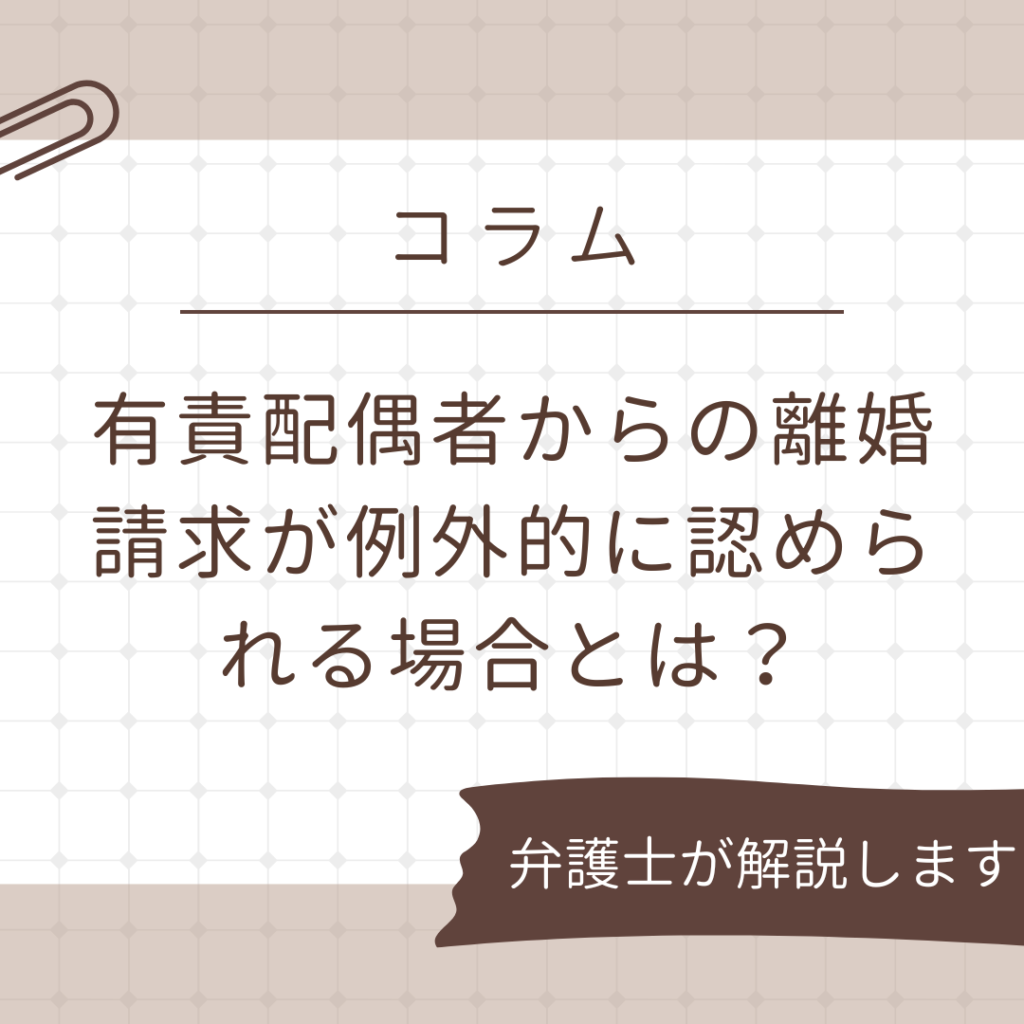
離婚をするためには、離婚することについて夫婦双方が合意をするか、合意ができない場合には離婚調停を申し立て、調停不成立の場合、離婚訴訟を提起する必要があります。
このとき、離婚を請求する側が不貞行為やDV・モラルハラスメントなどにより婚姻関係を破綻させた「有責配偶者」である場合に、そのような有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。
今回は、有責配偶者からの離婚請求について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説します。
「原則」は認められない
結婚は双方の合意によって成立し、離婚も双方の合意によって成立します。
また、夫婦双方の合意がなくとも、法律上定められた離婚事由(民法770条1項)が存在する場合には、夫婦の一方からの請求によって、裁判所が離婚を認めることとなります。
しかし、婚姻関係が破綻している場合に必ず離婚請求が認められるとすると、夫が離婚をしたいと考え、あえて不貞行為に及んだ場合などにも、夫からの離婚請求が認められてしまいます。
不貞行為をされた妻としては、夫の不貞行為により精神的苦痛を受けるうえに、離婚に応じる意思がないにもかかわらず離婚が認められてしまうこととなり、夫の離婚請求はあまりにも信義誠実に反する行為といえます。
そのため、このような有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
実際に、夫が不貞をし、妻に対して離婚請求をした事案で、最高裁昭和27年2月19日判決は以下のように判断し、夫からの離婚請求を認めませんでした(特徴的な言い回しのため、弁護士の間では「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれております。)。
「上告人〔夫〕が勝手に情婦を持ち、その為め最早被上告人〔妻〕とは同棲出来ないから、これを追い出すというということに帰着するのであって、もしかかる請求が是認されるならば、被上告人〔妻〕は全く俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくの如き不徳義勝手気侭を許すものではない。」(〔〕内は筆者による註記)
「例外的」に認められる場合
昭和62年判決
とはいえ、有責配偶者からの離婚請求が、すべて認められないというわけではありません。
不貞行為をした有責配偶者である夫からの離婚請求事件として、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(「昭和62年判決」といいます。)があります。
昭和62年判決は、有責配偶者からの離婚請求について、以下の3つの要件にあてはまる場合には、有責配偶者であることのみをもって離婚請求が許されないとすることはできないと判断しました。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間であること
②未成熟子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと
昭和62年判決が出されて以降、有責配偶者からの離婚請求は、上記3要件を基礎として判断されるようになりました。
3要件について
要件①
有責配偶者からの離婚請求事件において、別居期間が7年で長期間の別居と判断した裁判例があれば、別居期間11年で長期間の別居とはいえないと判断した裁判例もあります。
「両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間」とされているように、どれだけの別居期間が必要かは、各事案ごとに検討する必要があります。
要件②
未成熟子とは、親から独立して生計を営むことができない子供のことです。成人しているとしても、在学中であったり、身体的・精神的な障がいにより親から独立して生計を営むことができない子供の場合には、未成熟子として扱われることがあります。
未成熟子が存在しないことを要件としたのは、離婚によって未成熟子の監護・教育・福祉に悪影響が生じることを防ぐためです。
そのため、離婚しても未成熟子の監護・教育・福祉に悪影響がなく、そのうえで他の事情も総合して信義誠実に反しているといえない場合には、未成熟子がいるとしても、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
実際に、平成6年2月8日最高裁第3小法廷判決は、昭和62年判決の3要件を引用しつつ、次のように判断をして、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めました。
「有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排除すべきものではなく、前記の事情を総合的に考慮して右請求が信義誠実の原則に反するとはいえないときには、右請求を認容することができると解するのが相当である」
要件③
別居期間が長くなればなるほど、すでに離婚したのと同じような生活状態になり、離婚したとしても精神的・社会的に苛酷な状況に置かれるということは少ないでしょう。
そのため、離婚によって経済的に苛酷な状況に置かれるか否かの点を注視することになります。
経済的に苛酷な状況に置かれるか否かは、離婚請求されている側の収入状況、財産状況、離婚までの婚姻費用の支払状況、離婚後の財産給付が十分か、といった様々な事情を総合して判断することとなります。
おわりに
以上のように、有責配偶者からの離婚請求は、認められないのが原則ですが、例外的に認められる場合があります。
そして、そもそも有責配偶者に該当するか否か、有責配偶者に該当するとしても例外的に離婚請求が認められるか否かは、各事案に応じた法律上の判断が必要です。
そのため、離婚請求を検討している方はもちろん、離婚請求をされた方にこそ、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
横浜シティ法律事務所では、これまで多数の離婚問題のご相談を受け、解決してきました。
初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。


弁護士の山本新一郎と申します。
私は江戸時代より代々医師を生業としてきた家系に生まれ、幼い頃から病気に悩む方々に対して優しい言葉をかけ、懸命に治療をする父や祖父の姿を見て育ちました。
私が弁護士を志した原点もここにあり、法的トラブルに巻き込まれてしまった方々の負担を少しでも軽くしたいと常に考えております。
病気と同じく、法的トラブルも早めにご相談いただければダメージなく解決できるものです。
まずはお気軽にご相談ください。
離婚ひとつをとってみても悩みや答えは十人十色です。
思うまま、感じているままにお話しください。
一緒に悩み、考え、あなたにとって一番の答えを探しましょう。